シンクウキッチンでは、真空調理・低温調理の味つけに濃縮つゆ、いわゆる「めんつゆ」を推奨しています。
決して横着でもずぼらでもなく、おすすめするにはそれなりの理由があります。
真空調理・低温調理のコツにもつながるところなので、ぜひ目を通してみてください。
まずはおすすめ、ベーシックな4品を。
シンクウキッチンおすすめ濃縮つゆ4選
シンクウキッチンではあまから、濃口、淡口の3タイプに分類して使い分けています。

| 炭水化物 | 30~55g |
| 塩分相当 | 6~10g |
すき焼きの割下としてストレートで使用するタイプです。
じつは用途が広く、照り焼きやきんぴら、牛丼や豚の角煮、魚の煮付けなど幅広く応用できます。
おすすめは、創味 すき焼きのたれ
再仕込みしょうゆと三温糖のしっかりしたあまから味に、枕崎産のかつおだしがブレンドされたロングセラーです。

| 炭水化物 | 15~30g |
| 塩分相当 | 8~15g |
めんのつけつゆに最適化され、2~4倍に濃縮された濃口しょうゆの色が強めに出ているタイプです。
つけ・かけつゆはもちろん、煮もの、おでんや炊き込みご飯など、レシピ数もダントツに多くあります。
各社の主力がひしめく激戦区で参入メーカーも多数です。
つけつゆに最適化されているため、甘さは控えめなものが多く、煮ものに使う場合はみりんや砂糖などを足す必要があります。
おすすめは創味のつゆ

濃口タイプですが、煮ものなどの料理に特化した甘口もあります。
サイズ的に業務用ですが、用途が広いので意外とすぐに使い切ってしまいます。
おすすめは創味 煮物つゆ

| 炭水化物 | 15~30g |
| 塩分相当 | 10~22g |
関西圏では定番の淡口しょうゆがメインのタイプです。
※濃口でも淡口でも、原材料名ではしょうゆです。
濃口よりも淡く、白だしよりも琥珀色です。
各社で塩味の振り幅が広く、メニューにあわせて甘味の追加が必要です。
おすすめは創味 京の和風だし
1800mlの「和風だし」とは別物で、こちらの方が塩加減がマイルドです。
真空調理・低温調理の調味液の考え方
普段の料理では聞き慣れない言葉ですが、真空調理・低温調理では調味料とだしなどの液体をあわせたものを調味液と呼びます。
テクスチャを整えた食材に調味液を投入し、脱気密封してから恒温加熱します。
その際、調味液の量にも質(味)にも影響するのが水分であり、真空調理・低温調理の仕上がりを大きく左右する本質的な要素なのです。
量は盛りつけからの逆算
ほとんどの食材は、60%以上は水分で構成されており、水分を全く含まない食材を見つけるほうが難しいほどです。
水気などどこにも無いような干ししいたけでさえ9%の水分を含んでいます。
湿熱加熱では、熱が食材中心部へ向かうとき、水分は外へと向かいます。
反対に、湿熱で冷却するとき、水分は食材中心部へ向かって吸収されます。
食材をボイルやスチームで加熱すると、細胞のならびがくずれたり、たんぱく質がらせん状にねじれたりするため、水分や融解した脂質はしぼり出されるように溶出します。
「野菜をゆでると水っぽくなる」というのは見方によっては誤りで、じつは下ゆでしても成分の構成比は大きくは変わりません。
切片のあいだや切り口に付着する水分がそう感じさせるだけで、遠心脱水でそれらを取り除いてみると、重量はむしろ減少しているのです。
いつもの料理では、しぼり出された水分はお鍋の中に混ざり合い、増えたぶんも合わせて味つけされています。
当然ながら、盛りつけ後あまった煮汁にも調味料はしっかり使ってあるのです。
ところが、袋が鍋代わりの真空調理・低温調理では、盛りつけに必要な最小限の煮汁から逆算して味つけします。
先程の食材そのものから出る水分も含まれているため、ごくわずかな液体を追加するだけで全体にいきわたるのです。
しかも、脱気密封されているため、煮詰まることもありません。
したがって、真空調理・低温調理で使用する調味液(調味料)は、ふだんの料理の割合よりも高い濃度で調合されます。
質は食材の性質・特徴を加味する
湿熱加熱による脱水量は、野菜でおよそ10~20%、精肉では温度に応じて20~40%ほど減ってしまいます。
つまり、肉が多いほど調味液の濃度は低くなるということになります。
盛りつけに必要な量を求め、希釈を加減していくという手順になります。
水の割合は通常調理の半分になるというイメージ。
面倒な計算なのでツールがあります。
さらに、チャンバー式の真空パック機では、真空(減圧)することで食材中の気体や水分が膨張し、組織間にわずかな動きやすき間が生まれ、調味液が染み込みます。
シールを終え大気圧に戻す工程では、食材は逆に収縮するため、内部へ染み込んだ調味液はさらに深部へ向かって浸潤することになります。
真空調理・低温調理は、調味料が最小量で、味の染み込みもいいと言われるのはこのためです。
しかし、エアポケットの原因となる揮発成分や砂糖の溶かし込みなど、あらかじめ準備しておかなくてはならない作業も発生します。
その点、希釈して使用することが前提の濃縮つゆ、いわゆる「めんつゆ」は、これらの作業をすべて終わらせた調味液と考えることができるのです。
濃縮つゆの使用をおすすめする理由
真空調理に濃縮つゆをおすすめする理由は以下のとおりです。
食材の構成はそれほど変わらない
濃縮つゆ・めんつゆは、単にめんのつけつゆに最適化され、わかりやすい商品名が採用されたというだけで、根底の成り立ちはどれもしょうゆ+発酵調味料+だしの組み合わせです。
| ‐ | 主な食材 | かえし | 八方だし | めんつゆ | 濃縮つゆ | 煮ものつゆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| しょうゆ | 濃口・淡口 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 発酵調味料 | みりん・酒 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| だし成分 エキス類 | 昆布 かつおぶし 干し椎茸 酵母エキス たんぱく加水分解物 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 水分 | 表記されない | ◯ | △ | △ | ◯ | |
| 糖分 | 砂糖・三温糖・水あめ | △ | ◯ | ◯ |
つまり、全くの別ものではなく、かえしから家庭料理の煮ものつゆまで地続きです。
食品製造の技術革新により、だし成分やエキスと水が分離できるようになった頃から、濃縮つゆいわゆる「めんつゆ」が登場しました。
しょうゆメーカー各社が手掛けるだししょうゆは、しょうゆ加工品として基本的には(しょうゆ+だし成分+水)です。
すき焼きのたれやてりやきのたれも、基本的な構成はそれほど変わらないのです。
手軽で便利とは言っても、かつお本枯節や宗田節・鯖節など、一般家庭ではまず目にすることもないだし素材が使われ、まさに企業努力の賜物です。
到底、家庭で真似できるようなものではありません。
面倒な工程が省ける
もちろん、コストを優先し自分好みの配合で調味液を作ることもできます。
しかし、真空調理・低温調理ならではの面倒な注意点もあります。
調味液を使うことで省ける工程は数多く、少量調理の家庭向けでは特にその効率性も際立ちます。
アルコールの煮切り
エタノールは78.37℃を超えると気化し、その後温度の上昇に伴い膨張します。
脱気密封する前に煮切り処理などでアルコール分を抑えなくては、袋内で気体が膨張するため危険です。
具体的には14度のアルコール度数の料理酒を大さじ1杯だけ脱気密封し、湯せん加熱すると、95℃付近でソフトボールほどの大きさの気体になる計算です。
砂糖の溶かし込み
真空調理・低温調理の調味液は濃度が高く、さらに伝導熱が主体であるため袋の中では対流がほぼ起こりません。
砂糖などの糖類は加熱するだけでは溶けないため、あらかじめ撹拌して溶かし込んでおく必要があります。
とろみづけ
あんなどの調味液を作る場合も同様に、あらかじめとろみをつけておく必要があります。
冷却
真空調理・低温調理の脱気密封は、その精度を高めるためやポンプの保護ためなどを目的に、基本的に20℃以下まで冷ましてから行われます。
アルコールの煮切りや砂糖の溶かし込み・片栗粉でのとろみ付けなどのあとは、必ず冷却しなければ使用できません。
脂分の固形化や比重の変化なども留意しておく必要があります。
再現性が高い
真空調理の調味液は濃度が高く、さらに調理中に味を見ることはできません。
途中修正がきかないのです。
誰でも・いつでも・どれだけでも同じ味を再現するためには、不確定な要素はできるだけ減らしておく必要があります。
入手しやすい
地域性のあるしょうゆや蔵出しのみりんがおいしさの秘訣では、再現性も上がりません。
濃縮つゆであればごく普通のスーパーや一般的なネットショッピングでも入手できるので、ハードルはぐんと下がります。
計量・調合時のぶれ幅が小さい
1回の計量で味つけが終わるので、ぶれ幅は最小限です。
おもさのちがう複数の袋に分けても、投入するさえ合わせれば同じ味に仕上がります。
おいしい
濃縮つゆは市場は、しょうゆ・食酢・だし・調味料など多岐にわたるジャンルの食品メーカーが参入する大きなカテゴリーです。
すっかり家庭の常備調味料として定着し、売上自体が頭打ちに達した感じもあります。
スーパーの広くなった濃縮つゆコーナーをのぞくと、だし素材や訴求の見直しなどでシェアを奪い合う競争へと変化しているのがわかります。
これまでは強いだしの香りやアミノ酸系の添加物による複雑な雑味感など、特有の風味を敬遠する声もありました。
しかし、まさに日進月歩。
近年では、調理用途を主目的にした控えめな自然なだしの風味や、甘みを強めた煮もの専用の濃縮つゆなどバリエーションは実に豊富です。
ネットショッピングでは、小売市場にあまり出てこなかった業務用商品も購入できるようになり、「あのお店のおいしい味って、じつはこれだった!?」という楽しみ方も出てきました。
せっかく最小の使用量でコスパよく使えるのですから、各社のよりすぐりの一品を試してみてはいかがでしょうか?
濃縮つゆに使われる食材
人間は、基本五味の甘・塩・酸・苦・旨に辛・渋を加えた7種の呈味成分を、極めて個人差のある味蕾で感受し、同じく個人差のある語彙力で表現しています。
アミノ酸レベルで研究される濃縮つゆも、個人の好みや先入観だけでなく、慣れや親しみといった曖昧な感覚で大きく左右されてしまいます。
早い話、万人に共通するおいしいさをつくることはとても難しいのです。
また、濃縮つゆには化学的イメージの食材名や添加物も使われていることから、反射的に耳目をふさぐ方もおられることでしょう。
しかし、まずはどんなものが何の目的で使われているのか正しく知っておかなければ、「化調無添加、天然、有機・昔ながらこそ優れている」という優良誤認を起こしかねません。
濃縮つゆによく使われている食材のいくつかを少しだけでも掘り下げてみましょう。
しょうゆには下記の種類があります。
- 種類でわけると
- 濃口醤油(こいくちしょうゆ)
しょうゆ消費の8割はこいくち - 淡口醤油(うすくちしょうゆ)
関西生まれ:仕込み段階で食塩を1割多く用い、米を糖化させた甘酒を使う - 溜醤油(たまりしょうゆ)
中部地方生まれ:小麦が少なく、味噌玉麹を使って熟成させる - 再仕込醤油(さいしこみしょうゆ)
食塩水ではなく生揚げ醤油でもう一度仕込む - 白醤油(しろしょうゆ)
主原料は小麦
- 濃口醤油(こいくちしょうゆ)
- 製造方法でわけると
- 本醸造方式
大豆と麹菌・酵母・乳酸菌のはたらきでできた諸味(もろみ)を熟成してつくる伝統的な製法方法 - 混合醸造方式
本醸造方式でできた諸味(もろみ)にアミノ酸液などの分解調味液を加えて熟成させる製法 - 混合方式
本醸造方式で作られた生揚げ醤油にアミノ酸液などの分解調味液を加えてつくる製法
- 本醸造方式
- JAS規格規準でわけると
- 超特選
全窒素分(うま味成分)の数値が特級規準の1.2倍以上 - 特選
全窒素分(うま味成分)の数値が特級規準の1.1倍以上 - 特級
- 上級
- 標準
- 超特選
しょうゆには下記の種類があります。
- 種類でわけると
- 濃口醤油(こいくちしょうゆ)
しょうゆ消費の8割はこいくち - 淡口醤油(うすくちしょうゆ)
関西生まれ:仕込み段階で食塩を1割多く用い、米を糖化させた甘酒を使う - 溜醤油(たまりしょうゆ)
中部地方生まれ:小麦が少なく、味噌玉麹を使って熟成させる - 再仕込醤油(さいしこみしょうゆ)
食塩水ではなく生揚げ醤油でもう一度仕込む - 白醤油(しろしょうゆ)
主原料は小麦
- 濃口醤油(こいくちしょうゆ)
- 製造方法でわけると
- 本醸造方式
大豆と麹菌・酵母・乳酸菌のはたらきでできた諸味(もろみ)を熟成してつくる伝統的な製法方法 - 混合醸造方式
本醸造方式でできた諸味(もろみ)にアミノ酸液などの分解調味液を加えて熟成させる製法 - 混合方式
本醸造方式で作られた生揚げ醤油にアミノ酸液などの分解調味液を加えてつくる製法
- 本醸造方式
- JAS規格規準でわけると
- 超特選
例:全窒素分(うま味成分)の数値が特級規準の1.2倍以上 - 特選
例:全窒素分(うま味成分)の数値が特級規準の1.1倍以上 - 特級
例:全窒素分(うま味成分)の割合が1.5g/100ml以上 - 上級
例:全窒素分(うま味成分)の割合が1.35g/100ml以上 - 標準
例:全窒素分(うま味成分)の割合が1.20g/100ml以上
- 超特選
大豆や小麦(植物性たんぱく)や畜肉(動物性たんぱく)を酸や酵素で分解し、ペプチド(アミノ酸の結合体)アミノ酸を抽出して作られる粉末・またはペースト状の食材です。
1890年代にヨーロッパで確立され、1930年代には日本でも作られるようになりました。
製造技術と利用技術は主に醤油業界で改良進歩が行われてきた経緯があります。
得られる成分で味は違うので、たんぱく加水分解物といっても多くの種類があります。
アミノ酸系の複雑なうま味の付与のために使われます。
大豆のたんぱく質を麹菌(こうじきん)の酵素ではなく塩酸で分解したものを「アミノ酸液」といい、混合醸造方式や混合方式のしょうゆに使われます。
アミノ酸液をめぐる紆余曲折をさかのぼると、戦前戦後の食糧難、GHQの原料配分への介入、当時のキッコーマン㈱技術者による折衷案の提示など、激動の時代における先人達の苦労を垣間見ることができます。
酵母とはビールやパンなどの発酵に使われる微生物です。
発酵の役目を終えた酵母から、熱水や酵素の作用でアミノ酸や核酸などのうま味成分を抽出したものが酵母エキスです。
抽出する成分のバランスもさまざまですが、リキッド・ペースト・パウダー・微顆粒など形状もさまざまです。
うま味調味料だけでは得られない複雑な風味や呈味を持たせるために使われます。
(※呈味とは、甘味、塩味、酸味、苦味、うま味、辛味、渋味など、食品中で味を示す成分の総称)
食品成分表では食材として扱われます。
素材名〇〇+エキスの食材は多くあります。
鮮魚としてのかつおの風味を持つかつおエキス。
かつお節でとっただしの風味を持つかつお節エキス。
他にも、ビーフ・ポーク・チキンエキス、それらの総称の畜肉エキス、ホタテエキスや昆布エキス、野菜エキスなどがあります。
基本的には、煮出して濃縮したものを液状、または粉末状にした食材です。
素材特有の複雑味や凝縮されたうま味の付与のために使われます。
食品成分表の原材料名の/で区切られた後の部分は添加物が記載されています。
(/より前は食材)
また、調味料として添加される場合、物質名ではなくアミノ酸・核酸などに略称されます。
アミノ酸とはいわば生命の源です。
化石や隕石からも検出され、アミノ酸から生命起源の謎を解く研究がいまも続けられています。
自然界には500種以上のアミノ酸が存在しています。
そのうち20種、体内で合成できる11種の非必須アミノ酸と、合成できない9種の必須アミノ酸が人体のたんぱく質を構成しています。
アミノ酸は結合体の大きさで、アミノ酸→ジペプチド→ポリペプチド→たんぱく質を構成します。
アミノ酸それぞれはうま味・酸味・苦味・甘味など固有の味を持ち、LかDの型でも異なります。
舌の味蕾細胞にある受容体で検知され、脳にその情報を伝えるという鍵と鍵穴のような仕組みです。
調味料(アミノ酸)として代表的なものがL-グルタミン酸ナトリウムです。
昆布のうま味成分であるグルタミン酸に調味料として使いやすいようにナトリウムをつけて乾燥させたものがL-グルタミン酸ナトリウムです。
アミノ酸系のうま味が付与されます。
調味料(核酸)は、アミノ酸とは系統の違ううま味成分で、かつお節などに多く含まれるイノシン酸、干し椎茸を水で戻して加熱した際にあらわれるグアニル酸が代表的な核酸系のうま味成分です。
それぞれ単体でもうま味を持ちますが、グルタミン酸のうま味を強化持続させるブースターのような相乗効果が広く知られています。
とうもろこし澱粉から作られるぶどう糖(グルコース)を酵素の力で果糖(フルクトース)に異性化させたもの。
砂糖より安価なうえ、液状で扱いやすいため製造コストを大きく抑えることができます。
砂糖と同じ1gで4kcalの熱量があり、低温になるほど甘味が増すという特性があるため、清涼飲料水や冷菓に欠かせない甘味料です。
ぶどう糖<果糖(50%以上)
果糖分55%の場合、砂糖の甘味を100とすると100~120程度(温度により変化)
ぶどう糖>果糖(50%未満)
果糖分が42%の場合、砂糖の甘味を100とすると70~90程度(温度により変化)
ぶどう糖<果糖(90%以上)
単体で使われることは少なく、ぶどう糖果糖液糖と混ぜ合わせた結果として果糖ぶどう糖液糖ができあがると考察しています。
ぶどう糖果糖液糖に10%以上の砂糖を混ぜ、甘さを調整したもの。
マメ科の多年生植物の根から抽出される甘味料。
物質名はグリチルリチン。
植物由来の甘味、持続性、コク・厚みを持ちます。
複雑でまろやかな後味が特徴。
キク科の多年生植物の葉から抽出。
糖質はゼロでも砂糖の200倍の甘味を持ちます。
アメリカ、EUをはじめ多くの主要国で安全性が確認され、使用が認可されています。
植物由来の甘味、砂糖に比べると後引きのある優しい後味。
酸味や苦味のカバーができます。
食品に使われるもっともポピュラーな褐色の色素。
プリンなどの旧来のカラメルⅠとは別物。
液体または粉末で、天然・合成含め、全食品着色料の80%を占める。
使用の目的は茶褐色の着色だが、副次的効果としてロースト感の付与、フレーバーとの相乗効果、コク付けなどがあります。
EU、アメリカをはじめ世界の主要国で、常識的な摂取量での安全が確認、使用が認可されています。
濃縮つゆで作った真空調理・低温調理メニュー例






まとめ:低温調理・真空調理と濃縮つゆは相性抜群
- 低温調理・真空調理の味付けにはコツは水分コントロール
- タイプは大きくは3つ、あまから・こいくち・うすくち
- 使用食材について知っておこう
低温調理・真空調理と濃縮つゆの相性は抜群です。
掲載レシピの分量を目安として、お好みの濃縮つゆを好きな倍率で使っていただいてOKです。
シンクウキッチンのレシピ作成にあたって、以下の3つが考え方の軸になっています。
- 食材の60~90%は水で構成されている
- テクスチャを整える工程と、味をのせる・入れる工程を分けている
- 調味液の量は袋ごとの食材のおもさで決まる
あらかじめ、美味しく調味された濃縮つゆを使えば、しょうゆや砂糖といった調味料の計量は必要なくなります。
突き詰めれば、下ゆでと脱水で8割の仕事は終わり、あとはパックして機械任せで加熱しているだけなのです。
どっぷりはまる頃には、料理の概念も少し変わるかもしれませんね。
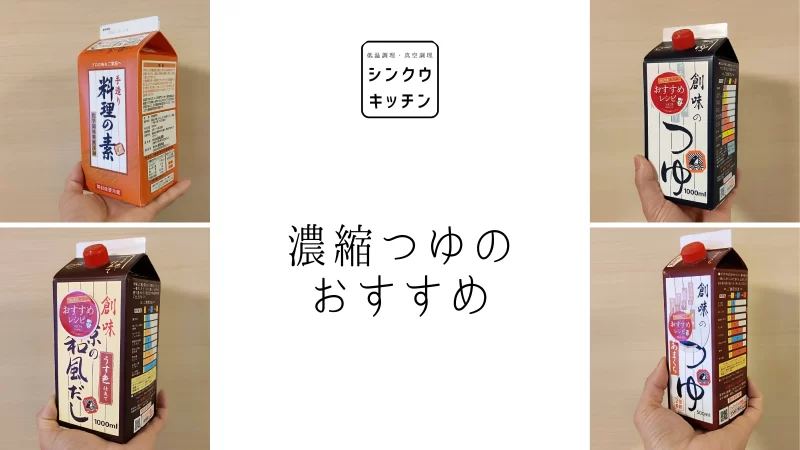






コメント